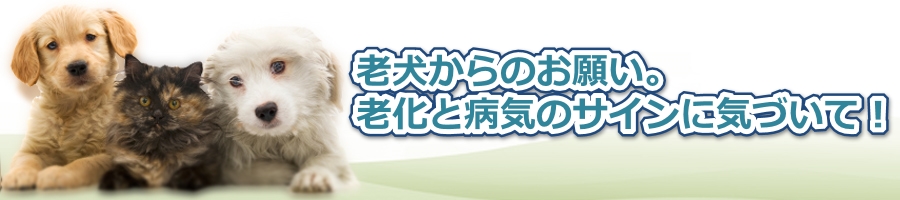犬が子宮蓄膿症になる確率は25%なんと4頭に1頭が子宮蓄膿症に!

犬の子宮蓄膿症を知っていますか?
犬の子宮蓄膿症は決して珍しい病気ではありません。
「子宮蓄膿症なんて、あまり聞かない病名だし・・・。」
「犬の子宮蓄膿症なんて、まわりになった犬がいないし関係ない」
なんて思っていませんか?
避妊手術を行っていない犬の25%、4頭に1頭が子宮蓄膿症に
なっています。あなたの愛犬も明日、子宮蓄膿症に
なる可能性も十分にあります。
子宮蓄膿症を発症しやすい年齢は5歳を過ぎた犬です。
避妊手術をしていない老犬ですと
更に子宮蓄膿症になる確率は上がります。
犬の子宮蓄膿症の症状、原因、手術方法、手術費用など
具体的に紹介します。
子宮蓄膿症の症状は?

多飲多尿、多飲の判断の目安は?
犬は水をよく飲む動物です。
散歩から帰ったあととか、激しい運動をした後とか塩分の多い
食べ物を食べた後など。
しかし、通常よりも多く水を飲んでも更に水を欲しがるときには注意が必要です。
たくさん水を飲むことによってオシッコの量も増えます。
「犬が子宮蓄膿症になったら水を多く飲むのは分かったけど
目安はどのくらいですか?具体的な量を教えてください。」
犬に限らず動物は1日に体重1キログラムに対して50〜60mlの水分を摂っています。
水からだけでなくて食べ物からも水分を得ています。
10キログラムの犬ですと大体ペットボトル1本ぐらいの水を摂っていることになります。
これは目安ですので、日頃愛犬がどれぐらいの水を飲んでいるのか一度キッチリと
計って健康な状態での水分摂取量確認しておきましょう。
陰部から膿や血膿が出て臭う
犬の子宮蓄膿症には二つのタイプがあります。
「開放性子宮蓄膿症」と「閉鎖性子宮蓄膿症」です。
犬の子宮頸部が開いているのが「開放性子宮蓄膿症」で
子宮頸部が閉じているときになるのが「閉鎖性子宮蓄膿症」です。
犬の子宮頸部が開いている状態のときは犬の子宮内に溜った膿や血膿が外陰部から
出てくると共に臭いがするようになります。
開放性子宮蓄膿症に対して閉鎖性子宮蓄膿症は犬の子宮頸部が閉じていますので
犬の子宮内に溜った膿は排出されずに子宮内部に溜り続けます。
(閉鎖性子宮蓄膿症でも膿が外陰部から全く出ない訳ではありません)
子宮が炎症を起こして膿が外陰部から排出されませんので
犬のお腹はハッキリ分かるぐらいに膨らんできます。
膿が外陰部から排出されやすい「開放性子宮蓄膿症」でも
膿が出てきた不快感から犬がすぐに膿を舐めとってしまうことが
ありますので注意が必要です。
食欲低下・食欲不振
犬は賢く繊細な動物ですので、ストレスも受けやすいです。
ご飯が変わった、近所で工事が始まったなどもストレスになり
食欲低下・食欲不振になったりします。加齢による影響もあるでしょう。
しかし、フードや環境の変化がなく急に
食欲低下・食欲不振になったのであれば犬の子宮蓄膿症など
の病気が疑われるので診察が必要になります。
今まで大好物だった「おやつ」などを急に食べなく
なったときも要注意です。
胃液などを嘔吐する。
犬が子宮蓄膿症になった場合の症状として
多飲多尿と同じぐらい多いのが「嘔吐」です。
子宮蓄膿症になって嘔吐する段階ですと食欲低下になって
食べていない状態ですので嘔吐物は胃液で、その状態は
黄色いネバっぽい液体です。
発熱、犬の平熱知っていますか?
犬の平熱は37度後半から39.0度程度と人間と比べると
高熱です。しかも、小型犬は大型犬と比べて平熱が少し高く
38.5〜39.0度ぐらいで大型犬は37.4〜38.5度ぐらいです。
犬が子宮蓄膿症などの病気になると39度後半ぐらいの
発熱を起こします。
しかし、子宮蓄膿症になった全ての犬が発熱するわけでなく
発熱がない犬もいますので判断に注意が必要です。
犬のアノ行動が子宮蓄膿症の原因かも?
犬が子宮蓄膿症になってしまう行動とは?
なぜ犬は子宮蓄膿症になってしまうのでしょうか?
犬の子宮蓄膿症の原因は細菌感染で大腸菌、ブドウ球菌、サルモネラの
細菌です。その細菌のなかでも大腸菌が7割ぐらいを占めていて犬の子宮蓄膿症の主な原因です。
「大腸菌が原因なのは分かったけど、なぜ子宮に侵入してしまうの?」
犬は排泄後に肛門周辺を綺麗にしようとして舐めてしまいます。
肛門と陰部は近いので肛門から舐めとった大腸菌が陰部から
膣、子宮へと侵入してしまって感染します。
「子宮蓄膿症の原因である大腸菌がなぜ子宮に侵入するかは
理解出来たのですが・・・・。犬の子宮蓄膿症には発症しやすい時期があるって聞きました。
犬は日常的に肛門周辺を舐めていますが、大腸菌が原因なら一年を
とおして子宮蓄膿症になってもおかしくないはずですが?」
その疑問は当然ですね。
通常の犬の子宮内部は精子や細菌が生存、繁殖出来ない厳しい環境にあります。
ですので、犬が肛門周辺から陰部を舐めて大腸菌がたとえ膣から子宮内に侵入しても
犬の膣内は高い酸性値(ph6から7)で
生存、増殖できませんので炎症も起こることはありません。
しかし、ある時期だけは犬の子宮内の免疫力が下がります。
そのある時期とは?
子宮蓄膿症が発症しやすい時期があるって本当?
本当です。
子宮蓄膿症になった犬のほとんどが同じ時期に発症しています。
その時期とは「発情期から1か月から2か月」です。
発情期には子宮の頸部が拡がり細菌が侵入しやすくなります。
発情期に子宮の頸部が拡がるのは受精のために精子が通りやすく
するためです。しかし細菌も子宮内部に侵入しやすくなってしまいます。
発情期が終わって、受精し妊娠している、いないに関わらず
2か月間は黄体ホルモンが分泌され続けます。
発情期が終わってこの黄体ホルモンが分泌されている
期間を「黄体期」といいます。この黄体期には受精するために精子または
胎児などを攻撃しないために子宮の免疫力が低下します。
子宮内部を精子と胎児に優しい環境にしてあげるためです。
しかし、子宮内部が精子や胎児に優しい環境ということは
犬の子宮蓄膿症の原因である細菌にも優しい環境ということです。
この黄体期の子宮内部は胎児を育てるために栄養も
豊富なのですが、それがまた細菌の増殖にも繋がってしまいます。
発情期に子宮頸部が拡がり細菌が侵入して、発情期が終わって
免疫力が低下する黄体期に細菌が増殖して子宮蓄膿症が発症(発情期から1か月から2か月目)される。
という流れになります。
知っておきたい病院での検査
超音波(エコー)検査
犬の身体に全く負担をかけずに無害で確実なのが
超音波検査です。
正常な子宮を超音波検査にかけても、画像に子宮がハッキリと
映し出されないのですが、犬が子宮蓄膿症になり子宮内に
膿が溜ると黒く映し出されてハッキリと診断出来るようになります。
また、レントゲン検査で子宮を検査すると膿の量が
ある程度溜っていないと分からないのですが、
超音波検査ですと、膿がほんの少しでも溜っていれば
映し出されて子宮蓄膿症と診断出来るのが
超音波検査の優れたところです。
レントゲン検査
犬の子宮蓄膿症の診断を確定するには
超音波検査でほぼ大丈夫なのですが犬の子宮だけで
なく犬の全身の状態を確認するためにレントゲン検査を
行います。
血液検査
犬が子宮蓄膿症になると血液中の白血球数が増加します。
子宮蓄膿症の末期になると白血球の数は減少に向かうことが
多いです。また血液検査では腎臓や肝臓の数値も把握出来ますので
犬が子宮蓄膿症の手術に耐えられるどうかが分かります。
子宮蓄膿症の治療には内科的治療と外科的治療があります。
子宮蓄膿症の根治には外科的治療しかありません!
犬の子宮蓄膿症の治療には
内科的治療と外科的治療があるのですが
根本的な解決としては外科的手術によって
犬の卵巣と子宮を摘出するしかありませんし
それが最良の選択です。ほとんどの獣医さんも外科的な
治療を選択されるはずです。
内科的治療と外科的治療のメリット、デメリットを
みていきます。
外科的治療のメリット、デメリット
犬の卵巣と子宮を全部摘出することを子宮蓄膿症の
外科的治療といいます。
外科的治療のメリット
外科的治療のメリットはなんと言っても「再発がない」ことです。
原因となる黄体ホルモンを分泌する卵巣と子宮自体を摘出するので
犬の子宮蓄膿症が再発するはずがありません。
外科的治療のデメリット
外科的治療のデメリットは犬の身体へ負担をかけてしまうことです。
子宮蓄膿症の手術は当然、全身麻酔を行います。
いくら腕のよい獣医さんでもリスクはゼロではありません。
そして老犬や体力的に問題がある子や心臓などに病気がある子も
外科的治療、手術へのリスクはあります。
内科的治療のメリット、デメリット
内科的治療のメリット
将来的に繁殖、子供を産ませる予定がある人は投薬などを中心とした
内科的治療法への選択になります。
黄体ホルモン分泌を抑える、プロスタグランジンなどのホルモンを
投与して治療します。
卵巣、子宮を温存しますので体力的、病気がある子などは手術での
リスクが当然、発生しません。
内科科的治療のデメリット
犬の子宮蓄膿症が発症しやすい時期
「発情期から2か月から3か月」のたびに発症してしまう可能性があります。
不妊手術をしていない犬の4頭に1頭が子宮蓄膿症になり
5歳以上の犬または老犬ですと子宮蓄膿症になる確率はあがります。
子宮蓄膿症になるということは
なりやすい年齢であったり環境や体質がありますので再発の可能性が
十分にあります。
黄体ホルモン分泌を抑制するホルモン剤を投与したり
犬の子宮頸部を開き子宮内部を収縮させ子宮内に溜った膿を排出する薬を注射をします。
薬のため子宮から膿が絶えず排出されますので犬はオムツを外せなくなります。
排膿されて汚れたオムツを日に何回も交換する飼い主さんの手間もあります。
「この子のためならオムツ交換ぐらい、なんともない!」と
思われるかもしれませんが、毎日毎日、子宮内に溜って独特の臭いの
する膿が付いたオムツを交換することを想像してみてください。
子宮蓄膿症の症状が無くなるまでずっと続くわけです。
愛犬も子宮蓄膿症になるたびに辛い思いをしないといけません。
飼い主のストレスだけでなく、愛犬自身も辛い思いをします。
発情期のあと、毎回、子宮蓄膿症になる訳ではありませんが
複数回、子宮蓄膿症になってしまう可能性があります。
そのたびに、病院に診察に行き子宮内の菌を退治する注射や排膿の注射を受け、体調不良で
しばらく過ごさないといけません・・・。子宮蓄膿症の内科的治療はかなりの時間を要します。
飼い主さんにもいろんな事情や思いがあるとは思いますが
愛犬のことを考えたら、やはり外科的治療で子宮と卵巣を摘出するのが最善です。
内科的治療は延命、一時しのぎと思ってください。
やはり気になる手術費用、検査費用など

犬の大きさや子宮蓄膿症の症状や地域などによって
かなり差が出てくるのですが手術費用は最低でも50000円は必要になります。
大型犬だと100000円ぐらいはかかります。
有名な腕のよい獣医さんだと倍ぐらいかかる話も聞きました。
なにせ、獣医さんは自由診療なので・・・・。
手術費用に加えて当然、検査費用も必要です。
血液検査や超音波検査が高くても5000円ぐらいでしょうか。
それに手術時に必要な麻酔が15000円から20000円。
点滴が10000円前後。
抗生剤や薬代も必要になります。
やはり、犬の個体差によって結構、手術の総額は
違ってきます。
開腹してみないと分からない状態もあるでしょうし。
手術を受けた犬の回復具合によって入院の日数も
違ってきます。
平均的な手術費用の総額として
小型犬や中型犬で100000円から150000円。
20キロを超えてくるような大型犬なら200000円を考えておきましょう。
勿論、獣医さんによって大きく手術費用は違ってきますので
手術前にしっかりと確認して予想を大きく上回るようなら
セカンドオピニオン、サードオピニオンも考えましょう。
また、クレジットカードの使用も大きな病院ですと可能に
なってきていますので、こちらも確認してみるのもありです。
日頃、通っているかかりつけの獣医さんなどでしたら
「じゃ、これぐらいでいいですよ」と想像よりも
安くしてくれたりもあり得ます。
子宮蓄膿症の手術はどのぐらいの時間がかかるの?

犬の子宮蓄膿症の外科的治療、卵巣、子宮の
全摘出手術に要する時間ですが、やはり犬の子宮蓄膿症の
状態に大きく作用されます。
目安として小型犬や中型犬で子宮から膿がお腹の中に
漏れていない状態ですと、早ければ30分、遅くても1時間半ぐらいで
子宮蓄膿症の手術は完了するようです。
愛犬の手術が始まって心配でたまらない飼い主さんからしたら
30分でも長い長い時間だと思いますが、開腹して卵巣、膿で腫れあがった
子宮の全摘出から縫合を考えると思ったより早い印象です。
大型犬は小型犬や中型犬と比べて手術時間がかかるようです。
卵巣は犬の背中側にありますので、開腹して犬の卵巣を開腹した
箇所まで、取り出さないといけません。
特に大型犬の肥満気味の犬ですと脂肪が邪魔をして
子宮蓄膿症の手術時間が更にかかるようです。
子宮蓄膿症の手術の縫合の傷口は10センチぐらいなのですが
大型犬になると当然、傷口も大きくなり縫合にも時間がかかってしまいます。
子宮蓄膿症の手術後、気をつけてあげたいこと。
子宮蓄膿症が初期の段階で発見できて症状も
重くない犬などは子宮蓄膿症の手術をして翌日に退院、
帰宅して一気に元気になり、食欲も元に戻りガツガツ食べる犬もいるようですが
やはり、犬の子宮蓄膿症は病気が進行してから見つかることが多く
緊急の手術、入院になる場合が多いようです。
子宮の状態にも大きく左右されるのですが
やはり,2〜3日の入院、長いと1週間ぐらい延びるようです。
帰宅してから気をつけてあげたいこと。
子宮蓄膿症の手術後の数日間は出血があります。
卵巣、子宮は摘出していますので、そこからの出血ではなく
膣に残った、血の混じったおりものなどがまだ出てきます。
この「血の混じったおりもの」も膣に残ったものが出てくるので
通常3日ぐらいで出なくなります。もしそれ以上、1週間しても
まだ出血があれば急いで獣医さんに診察してもらいましょう。
子宮蓄膿症の手術を受けた犬が膣炎を起こしていることも
考えられますので。
手術後に気をつけてあげたいことは、卵巣、子宮の摘出手術ですので
避妊手術をしたのと全く同じことになります。
避妊手術をした子と同じように、手術後は太りやすい体質になりますので
肥満予防に気を付けあげないといけません。