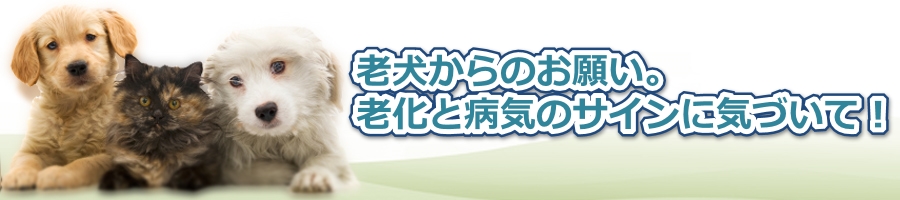肺気腫には慢性と急性があります。肺気腫の症状とは?
老犬・犬が口や鼻から泡や涎をだして呼吸困難になっているのは
急性の肺気腫かもしれません。
少しでも早くに治療を開始しないと急性の肺気腫は死に至る可能性もあります。
では慢性の肺気腫はどのような症状をみせるかといいますと
- 散歩や運動を嫌がるようになる。
- 疲れやすくなる。
- 呼吸時のはく時に辛そうにする。
- 運動後荒れた呼吸がなかなか落ち着かない。
などがあります。
慢性の肺気腫ではその症状が徐々にしか進みませんので
発見が遅れて死に至ることもあります。
散歩などから帰ってきて
少し呼吸が荒れていたりしても、その原因がまさか肺気腫からの
呼吸の乱れとは思いませんので・・・。
「今日の散歩は少し疲れたのかな?」ぐらいにしか思わないかと・・・。
急性の場合にはいきなり出る症状が
口や鼻から泡やよだれを大量に出して呼吸困難に陥り
苦しみますので、肺気腫と分かりますが。
気管支の先に多くの肺胞があるのですが
この肺胞には静脈血が流れ込んできて流れこんできた二酸化炭素を
酸素と交換するという極めて重要な働きをします。
この肺胞が何らかの原因で空気を必要以上に取り込んでしまって
最終、肺胞自体が破壊してしまう病気です。
また、肺の中に充満した空気が
収まりきらずに胸や首周辺の皮膚の下に溜って
しまう「皮下気腫」の症状を見せます。
皮下気腫の症状とは?
この皮下気腫の具体的な症状は
痛み自体はなく犬が痛みを訴えることはないのですが
飼い主などが犬の皮下気腫の患部を触ってみると
独特の感触で皮下気腫と判断することが可能です。
どのような感触かというと
握雪感(あくせつかん)雪を握ったり雪を踏んだりしたときの
感触とそっくりな感触があります。
また、捻髪音(ねんぱつおん)これは髪の毛をひとつまみ指で
つまんでこすり合わせた時の音のような感触があります。
また状態によっては「プチプチ」と犬の皮下で
空気がはじけるような音がする場合もあります。
肺気腫の治療をすれば皮下気腫は自然と
治癒しますが、もしも症状が治まらないようであれば
皮膚切開して溜っている空気を排気します。
老犬が口や鼻から泡やよだれを出していたら
肺気腫を疑ってみて老犬の喉や首周辺を
触って皮下気腫の症状がないか確認しましょう。
犬の肺胞が膨張して
肺気腫の原因は肺胞が膨張してしまって
壊れてしまうことによって起こる病気です。
肺胞と聞いてどのようなイメージが浮かぶでしょうか?
肺胞は非常に小さい組織というイメージがある方も多いと思いますが
なんと肺胞は肺の全容積の85パーセントを占める組織です。
具体的には肺胞は非常に弾力性のある器官で
その弾力性のおかげで吸い込んだ空気から酸素を
最大限に取り込んで血液中に供給して
循環してきた炭酸ガスと交換して呼吸として
体外に吐き出す重要な働きをしています。
しかし、何らかの原因でこの肺胞が弾力性を失い
空気を吸い込んだ時に膨らみきった風船のようになり
吐き出す・ガス交換が出来なくなります。
肺気腫になった犬が呼吸の時に吸うときよりも吐くときに
より苦しそうにするのは、そのためです。
また、肺胞が破壊されてしまう原因に
犬が気管支炎を発症していたり、気管支に腫瘍などがあって
気管支を塞いでしまっていて結果、空気に通り道が狭くなって
ガス交換を行っている肺胞に負担をかけて
肺胞組織が破壊されて肺気腫になる場合もあります。
肺気腫の他の原因としては
普段あまり運動をしない犬が何かの拍子に急激に無理な運動をして
日頃急激な呼吸運動に慣れていない肺胞が一気に酷使され
肺胞の組織が破壊されて急性の肺気腫を起こすことがあります。
肺気腫の原因に有害なガスを長期間に渡って吸い込み続けたことがあるのですが
身近な有害なガスにあたるのがタバコです。
タバコの副流煙による受動喫煙が危険であることは知られていると思います。
タバコを吸っている人が吸う煙を副流煙に対して「主流煙」と言うのですが
なんと主流煙よりも副流煙の方がタール・トルエン・メタンなどの
発ガン性物質を含む有害物質を多く含んでいます。
短期間なら副流煙を吸っても、そんなに老犬・犬の肺・肺胞はダメージを受けないでしょうが
何年も副流煙を吸い続けていたとしたら、肺胞はかなりのダメージを受けて破壊されているはずです。
肺気腫は肺胞がどのぐらいの割合が破壊されたらハッキリとした症状と現れるかというと
なんと肺胞の半分近くが破壊されないとハッキリとした症状が出ません。
急性の肺気腫なら一気に呼吸困難などを起こして飼い主にも分かるのですが
慢性の肺気腫だと徐々に病気が進行していますので
「今日の散歩は少し疲れたかな?」ぐらいに感じている間にも
肺胞の破壊は進んでいます。
その原因が家族の中の喫煙の副流煙であるならば
老犬・犬は避けられない環境で暮らしていることになります。
毎日少しずつ副流煙を吸い続けて
肺胞が破壊されて運動機能が低下して散歩も困難になってきます。
慢性の肺気腫は初期では発見が難しく肺胞の破壊がかなり進行してから
発見される場合が多いです、また死亡に至ることも決して少なくありません。
家族のタバコが老犬・犬の肺気腫の原因になるかもしれません。
治療の方法はあるの?
肺気腫の診断は息を吸うときではなく息を吐くときに
苦しがっているかどうかが判断の基準になります。
また動物病院ではエックス線検査を行い
本当に肺気腫なのか、他の呼吸器の疾患であるかを
診断します。
気管支炎などが原因で肺気腫を起こしている場合には
気管支炎の治療を行えば、完治に至ると同時に

自然に治ることもあります。
気管支炎の主な原因は気管支がウィルスやマイコプラズマなどに感染して
炎症を起こしてしまうことにあります。気管支が炎症を起こすとこによって
気管支内面の粘膜が炎症を起こしてしまって腫れあがってしまい
気管支内の粘液量が増加し気道が狭まって、呼吸が困難となり
「ゼーゼー」といった苦しそうな呼吸音が聞こえるようになります。
この炎症を起こしている気管支周辺の肺胞は破壊されてしまい
肺気腫となってしまいます。
気管支炎が原因の肺気腫であるならば
早期の段階で発見、治療を行えば肺胞の破壊も
最小限で抑えられ、完治もしやすく自然と治る可能性も高くなります。
外傷などが原因となり肺気腫を起こしている場合があります。
何らかの外傷(怪我)の衝撃で肺胞が破壊されて
肺気腫となり、呼吸が困難になっている場合もあります。
人でも交通事故などで衝撃を受けて
「なんだか原因が分からないけど事故以来呼吸が苦しくて疲れやすい」と
悩んでいた人が詳しい検査をしてみたら肺気腫だったということがあります。
ましてや、老犬ともなれば、若い時とは違い
少しの衝撃、例えば階段を踏み外して打ち付けたなどでも
大きな外傷の原因となります。
この場合も外傷の治療をしっかりと行えば
その衝撃によって破壊されてしまった肺胞以外の
肺胞破壊に拡がることはありませんので
自然と治る可能性が高いです。
残念ですが一度壊れた肺胞は元に戻ることはありません。
老犬・犬が口や鼻から泡や涎(よだれ)を出して呼吸困難になる
急性の肺気腫ならば症状がでている時点で直ぐに動物病院で
適切な治療を受ければ肺胞の壊れる割合も少なくて
老犬・犬のその後の生活もそんなに変化を要しなくても良いでしょう。
しかし、長い期間をかけて肺胞がじわじわと破壊されてきた
慢性の肺気腫では肺胞の破壊も拡がっており

有効な治療法は現在ありません。
現在の肺気腫の状態を維持しながら
今以上に悪化させない保存療法が目標となります。
出来るだけ清浄な環境を用意してあげて
決して無理な運動などをさせないように心掛けましょう。
呼吸困難になっている老犬・犬に絶対にしてはいけないこと
肺気腫で呼吸困難になり
口や鼻から泡やよだれを出しているのをみて
慌てて応急処置をしようとしてスポーツ用の高濃度の酸素スプレーなどを
犬に吸引させる人がいますが、これは絶対にしてはいけないことです。絶対にです。
肺気腫になってしまい、呼吸困難が激しいときなどに
治療の一環として酸素吸入を行いますが
これは獣医師の指示により行わる行為です。
獣医師の指示により行われる酸素吸入では
きちんと酸素濃度を調整した、ボンベなどでの酸素吸入が行われます。